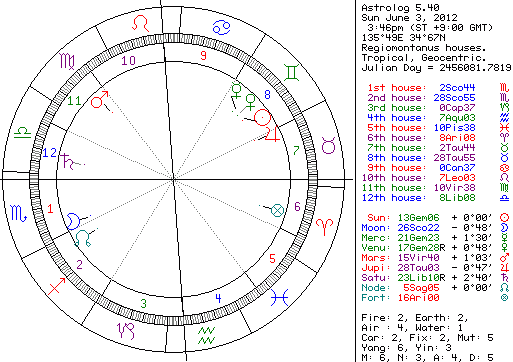用語解説 アスペクト
アスペクト(西洋占星術)

◆ アスペクトとは・・・
● 西洋占星術で用いられる アスペクトは、サイン同士のことがベースになっています。それを観察した後に、惑星の角度による角度に従ったアスペクトを探す事になります。
● アスペクトについて書かれた多くのテキストに、それは サイン同士のことであると書かれています。 マニリウスのアストロノミカ(1世紀)しかり、トレミーのテトラビブロス(2世紀)しかり、アル・ビルニ(エレメント・オブ・ザ・アート1029年)しかり、グイド・ボナタス(リバーアストロノミア1491年)しかり、イブン・エズラ (ビギニング・オブ・ウィズダム1148年辺り)等々。ケプラーがマイナーアスペクトを提案する(1602年)まで、ずっとず~っと占星術の歴史を通じて、アスペクトはサイン同士のことでした。
● どうして惑星同士のことだけになってしまったのでしょう? でも、アスペクトと思われている中の一つだけは、昔から、ずーっと、惑星同士のことでした。
それはコンジャンクションのことです。アスペクトは『ちらりと見る』という意味です。自分のまつ毛が見えないように、コンジャンクションはアスペクトの概念を外れています。そこでコンジャンクションのみ、惑星同士のことになっていて、そしてテキスト類は口が酸っぱくなるくらいにこの点に注意を添え、「コンジャンクションだけはアスペクトじゃない」と書いています。
● 西洋占星術で使われるアスペクトの定義から
● Aspect: 英和辞典での意味は、1,外見、容ぼう、表情 2,局面、様相 3,方位、向きなどとなっています。ラテン語では、aspectus、complexa、等。
● 西洋占星術的な意味では、アスペクトは見ること・見える事と関係があります。とある場所から、とある別の場所が見えるという感覚です(behold)。惑星同士が見えるという意味と、サイン同士で見えるという意味があり、どちらに優先順位を置いているかというと、トラディッショナルな占星術では、サイン同士の方が先でした。
※テトラビブロス 1-13
● 惑星はオーブというものを持ちます。太陽に惑星が近付くと一定の間隔の間、見えなくなるという所から考え出されました。そして、オーブ同士で関わることも、遂には、惑星同士の角度による角度に従ったものも、アスペクトと言われるようになりました。
● 『星の階梯 II 』では、アスペクトをコンジャンクションで解説していますが、便宜的にコンジャンクションで説明しているだけで、厳密にはコンジャンクションとは違います。コンジャンクションは、15度以内の同じサイン内にある惑星同士のことです。
● 『テトラビブロス』(1世紀の占星詩)には、アスペクトの定義があります。それは、360(全円の度数)と12(サインの数)の両方を、1から12までの整数で割って、整数の商を得るもの、とあります。すると、
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 12
の6つの答えを得ます。1はコンジャンクションですから、「見る」という概念を外れます。12は、それは取りも直さずサインである、としてアスペクトから退けます。都合、2(180度)3(120度)4(90度)6(60度)の4つが残ります。それらがアスペクトです。

● 9世紀の占星術師アブー・マシャー(Abū Ma'shar・9世紀)は、 360度を整数で割るという考え方を残しながら、5,8,9,10、18、20、30、・・・ 等も整数の商を得るけれども、それらはアスペクトという概念にそぐわないと論理的に説明しています。
例えば、5で割ることで72度のアスペクトのようなものができますが、それは、♌のサインと♏のサインとのアスペクトのことなのか、♌のサインと♐のサインのアスペクトのことなのか不明になってしまい、サイン同士のアスペクトのことを考慮できないので、アスペクトではないとします。他の整数で割れるアスペクトと思われる数字の解も、総じてそうなってしまいますから、アスペクトではないと説明します。
◆ ケプラーが数学的な美しさに魅了される
● 天才数学者ヨハネス・ケプラー(16~17世紀)は、アブー・マシャーの見解を読むことができませんでした。彼は西洋占星術も研究していて、もっとハウスの概念を知りたい、とか72度もアスペクトだなんて言い出します。(※ 知識を得たくても、得られないこともあるのです)
数学者ケプラーは惑星同士による、360度を整数で割れることを基本としてアスペクトを発表してしまったのです。何せ、大数学者先生ですから、その人の言うことなら間違いないだろう、ということで瞬く間にヨーロッパ中を席巻します。ウィリアム・リリー(17世紀)などもネイタルの判断でマイナー・アスペクトを使っています。
またしても…という感があります。歴史の変遷を押さえないと西洋占星術を把握できません。
◆ アスペクトの働き
● アスペクトにはいくつかの働き(作用)があります。
- 光を手渡す
- 性質を手渡す
- 力を手渡す(力を持たないと手渡せない)
- 意向をゆだねる(委任する)
- 物事を成し遂げる(マネジメント[執り行う] )
- タイミングを表す(執り行う時期)
- 光を持ち運ぶ(背負う)
これらの説明は、アスペクトの概略を述べた後の方で説明します。
アスペクトの、I II III
■ 西洋占星術のアスペクト I

● 上の図では、火星が射手のサインの26°にあり、そのオーブを広げていくとトラインでは一般に6゜のオーブ [トラディショナルな占星術では火星は片側8度のオーブを持つ] を認めますから、土星とトライン・アスペクトを形作ることになります。
しかし、トラディッショナルな占星術では、サインを外れてアスペクトを取ることはありません。火星の入っている射手のサインと、土星の入っている牡牛のサインは150゜で、アスペクトしない位置にあるからです。
● サイン同士ではアスペクトしていません。でも、オーブではアスペクトしている。この矛盾は、まったく矛盾ではありませんでした。何故ならば、アスペクトは、サイン同士のことに基礎を置いていたからです。射手のサインと牡牛のサインはアスペクトしません。ですから、まずは、考えを及ばせません。
その後、惑星が動いていること、オーブを含めて惑星同士のことへ、考慮を加えていく事になります・・・
ですから、古代の占星家たちも惑星同士のアスペクトを観察しています。
つまり、
● アスペクトという概念は、三つのものが組み合わさっています。
A.サイン同士のアスペクトが基本にあります。
B.惑星同士の、オーブによる考慮がなされます。
C.惑星の動きによって、完全なアスペクト(角度による)になるかならないか、の考慮が加わります。
● Cは、曲解され易いものです。
アスペクトというのはサイン同士の事柄がベースにあって、トラインであれば全て同じ性質のサイン同士で起こります。牡羊のサインはホット&ドライなサインとして、ホット&ドライな獅子のサイン、射手のサインとアスペクトします。同じ性質同士ですから調和がとれます。この両サインに惑星が一個ずつ入っていれば、それはトライン・アスペクトでした。オーブを無視してくサイン全体に及ばせています。しかし、タイトであればあるほど影響力も強いことをも認めていました。これが120度が調和がとれているという理由です。
惑星同士のオーブに入っていても、ベースになっている概念に当てはまっていないとアスペクトとは呼べません。しかしながら、
やがてアスペクトになる状態や、関係性は、今もアスペクトしているという関係と違う状態でありながら、判断の内容に密接に関わってきます。何故なら、西洋占星術では、惑星が動いていることも考慮に入れるからです。
コンジャンクションとは、言語学的に交接と関係があります。問題の惑星は隣同士のサインにあるとします。各サインの間には壁があることと見立てます。いわば、ドアを隔てて性的な交接関係を持とうとするわけです。できるでしょうか? もちろん、天上を見上げても、隔たりや壁などはありません。サインの境界を決めているのは占いだからです。しかしながら、その境界線に力がもたらされているのは天の決めた取り決めを人間が見つけたようなもの、神の存在なしには考えられません。だから、謙虚に襟を正す必要があるのです。やがてコンジャンクションするという状態と、今、コンジャンクションはしていないという状態の二つは厳密に区別する必要があります。
◆ いくつかの例で、アスペクトを説明していきます
● 一方の惑星が牡羊のサインの28度にあり、もう片方の惑星が獅子のサインの2度にあって、角度上94度のクォータイル・アスペクトをしているように見えても、牡羊のサインはホット&ドライ、獅子のサインもホット&ドライですから、この場合、トライン・アスペクトしていると捉えます。分度器は要りません。
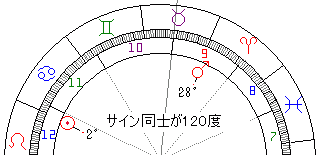
上の図の太陽と火星は、トラインです。クォータイルではありません。(部分的にはそう見えるので、パータイル)なクォータイルと書かれているモダンなテキストもありますが、間違っています。上のアスペクトはトラインです。ホット&ドライと、ホット&ドライなサイン同士でアスペクトしているからです。
● 西洋占星術上アスペクトは、判断を行ううえでとても重要ですけれども、全てではありません。ウィリアム・リリーはアスペクトにリセプションが含まれていないか常に注意を怠りませんでした。(これを明示的に書いている文章はありません。例題がそれを示しています。例えば、C.A 401p)
惑星のアスペクトはタイミング・機会を表します。歴代の占星家はそこにリセプションが加われば容易さが加味され、事柄の成就が助けられると考えてきました。従って、アスペクトは常にリセプションを参照しながら観察していくことになります。リセプションからアスペクトを探すよりも、アスペクトがリセプションを為しているかどうかを探す方が簡単です。
● 例えば恋愛の問題なら、アスペクトは、好きな人に会える機会があるのかどうかを示しますが、だからといって、それで全てハッピーエンドになるかどうかは別の視点が要ることになります。
● サイン同士でアスペクトするそれぞれの種類では、セキスタイル・アスペクトはわだかまりのない状態で会えることを示します。クォータイル・アスペクトは何かしら障害を乗り越えて会うような感じです。トライン・アスペクトは最も容易に会える印です。オポジション・アスペクトは、障害を抱えたまま会うという意味を含みます。
判断がこんがらがり始めたら、ディグニティー、リセプション、アスペクトに戻ることです。そして惑星の役割を変えて、最初から考え始めます。星占いに必要なのことは、これらの複合されたものを文脈(質問)ごとに読み解くことです。そうやって、くり返しくり返し、出口を求めるジグソーパズルのように解いていく必要があります。
● 下図の90度のアスペクト、クォータイル・アスペクトは、ホットと、もう一方は必ずコールドのサイン同士で起こります。つまり牡羊のサインの28度と蟹のサインの2度にある惑星とは、そのサインの性質が異なっていることから、スクエア・スペクトであり、調和を欠きます。
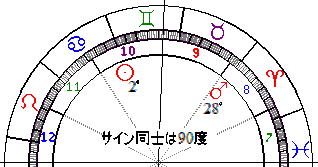
■ アスペクトしない・・・
角度差が122度となる、牡羊のサインの29度と乙女のサインの1度では、どう考えていたのでしょう? サイン同士のアスペクトでは150度の位置ですから、アスペクトしていないとして扱ってきました。今でも、そう扱わないと読み間違えます。それぞれ隣同士のサインもアスペクトしません。

■ オーブは惑星に固有です。アスペクトに付いている物ではありません
- オーブは、アスペクトではなく、惑星が持つものです。
● この見解も、既にアブー・マシャーが書いています。(he Great Introduction to the Science of the Judgments of the Stars VII. 3)
● ですから、アスペクト毎に、オーブを変化させる必要性はありません。
● 今日、オーブは、アスペクトによって変わるものだと考えられている節があります。アスペクトがオーブを持っていると思われています。
これでは、まるっきし、西洋占星術の理解が、ベースから違います。
ですからアスペクトの種類ごとに、オーブを変化させる必要性はありません。
オーブは、惑星に固有のもので、
- 土星 9度 半径
- 木星 9度 〃
- 火星 8度 〃
- 太陽 15度 〃
- 金星 7度 〃
- 水星 7度 〃
- 月 12度 〃 です。
サインの同士のアスペクトを考慮した後に、惑星同士の角度による角度に従った正確なアスペクトが完成されるか、完成されないのかを判断します。
■ オポジション
オポジション・アスペクトは、Hot なサインと Hot なサイン同士で起きます。親和性はどう考えたらいいのでしょう? ここに書いたアスペクト全ての事柄は、マニリウスのアストロノミカ、トレミーのテトラビブロスに詳しく述べられています。このオポジションですが、親和性はあると書いてあります。と同時に、サイン同士をよく観察すると、巨蟹宮と磨羯宮ではあまりにも季節が違いすぎる夏と冬だ・・・ だからそこでは親和性が無いし、一方秋と春では、季節こそ違うが太陽が昼に留まる時間は同程度であるから、かなりオポジションといえども親和性があるのだ・・・ と書かれています。つまり、オポジションは、サインによってかなり親和性に違いが出る位置と捉えられているようです。
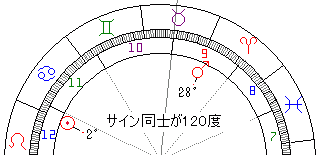
■ コンジャンクション
コンジャンクションは惑星同士のことです。
(コンジャンクション=惑星同士のこと)
コンジャンクションはアスペクトじゃないからね。
( コンジャンクション≠アスペクト)
↓
惑星同士のことは、アスペクトじゃないからね。
(惑星同士のこと ≠ アスペクト)
● 上のように理解すると幾分、理解し易いでしょう。
● コンジャンクションしているのか、アスペクトしているのか?
アスペクトとコンジャンクションは厳密には違いますが、同等に扱っても大きな問題が生じませんので、取り混ぜて説明させてください。惑星がコンジャンクションする、アスペクトするという場合、コンジャンクションしている、アスペクトしているかどうかを述べるのはひじょうに難しい問題? いえ、とても単純で簡単です。下図で天秤のサインの29度に太陽、蠍のサインの1度に土星。これはコンジャンクションしているでしょうか?

● 情報の量に惑わされると、これまでも少ない情報の中に真実が在ったかもしれないのに、それが見過ごされていきます。日本語の本に書いてあるから・・・ は、そんなに重要な事ではありません。これからも、活字になったものはそうやって人々を惑わし続けますが、それも人の世ならではのことです。情報の質にも目を向けるべきですが、これはとやかく言うより、自分で確かめるしかありません。疑問に思ったら確かめることです。それが英語でもギリシャ語でも、他に手が無いか、先生がいらっしゃれば先生におたずねになり、どんな本を読んだらいいか確かめるべきです。そして実占に際して、実例を使って調べてみるという態度で臨むのが良いと思います。
■ 西洋占星術のアスペクト II
惑星は、互いにアスペクトしたり、そのアスペクトで他の惑星の状態を左右したり、更には、多くの様々な働きが備わっています
1.見る
2.結びつく(接合)
3.物事を成し遂げる(マネジメントする)
4.タイミングを表す(執り行う時期表示)
3.離れていく
4.進行方向に接合する惑星が無いとき
5.進行方向にサイン丸ごと接合する惑星がない
7.光を持ち運ぶ(背負う)
8.光を委ねる(性質を)
9.光を委ねる(力を)
10.光を委ねる(性質と力を)
11.8及び9を使って、惑星同士を結び付ける(トランスファー・オブ・ライト)
12.8及び9を使って、惑星同士を結び付ける(コレクション・オブ・ライト)
13.光の反射
14.妨害をする
15.受け取れない光を元に戻す
16.後戻りして、光を与えない
17.後戻りして、他を妨害する
● 1.光を手渡す
■ サインの境界は、絶縁体のように作用します。
サインの境界が作用する事は、天の取り決めを人間が見つけたようなもので、自分勝手なイメージで占星学を作り直すことはできません。西洋占星術を様々な方法で作り変えている人たちを見ていると、地球の汚染の小さな雛形を見る思いです。サインの占星学的な有用性は別のページに譲るとして、状況が変われば(蠍のサインに入れば)、太陽と土星はコンジャンクションすることになります。
オーブ(惑星の持つもの)を勘違いしている人達も、多くは、惑星がオーブを持っていると思っていらっしゃいます。でも、惑星がオーブを持つとハッキリ書いてある書物が有るでしょうか? モダンな占星術ではアスペクトがオーブを持っていることになっています。それが証拠に、モダンな占星術では、木星と火星のトラインアスペクトのオーブと、天王星と海王星のトラインアスペクトのオーブは同じでありながら、セミセキスタイルとなるアスペクトのオーブは違っていきます。そして、コンジャンクションの場合は最大幅のオーブを認めることになります。
『あれ? 惑星が持っていると思っていた。』思いこみに過ぎません。
明らかにアスペクトが持つと書かれているのに、オーブは惑星が持つと勘違いをしているだけです。でも、この勘違いは惑星が持っているオーブと、人間が持つオーラを混同する考え方から出てきたもので、決して不幸なことではありません。感覚的に、惑星がオーブを持つことをどこかで把握していらっしゃる証拠です。そして、惑星こそオーブを持つ、それが正しい見解です。この感覚が大事です。
ジョン・フローリー氏は、著書「リアル・アストロロジー」の中で、これについて痛烈な批判をしています。
『モダンな占星術ではアスペクトが力を持っているように書かれている。アスペクトは惑星にさえできないことを成し遂げるかのようである。アスペクトは線に過ぎない。』
惑星こそオーブを持ち、働く力を持っています。ここで、アスペクトの概念B.だけを取り出すと、コンジャンクションなり、アスペクトなりになるわけですが、占星術ではA.の概念(サイン同士)に当てはまって始めてB.→C.と進んで行けることになります。
A.という基礎(サイン同士)はどこまでも基礎として成り立っていないといけないのです。下図をご覧下さい。最初にA.イン同士のアスペクトから見ると、トラインです。角度差から見るとクォータイルに含めたくなるでしょう。B.の概念(オーブによる)では、オーブによるアスペクトをしていません。C.の概念(角度による完成)では、ほとんどのチャートでは水星と土星が角度によるトラインになる前に、それぞれが他の惑星と別のアスペクトを完成させてしまうことが予想されます。
このような惑星の配置は、状況が変わってどうなるか等の質問では重要な視点になる場合が多々あります。例えば、仕事を変わるとか、上司が替わるとか、住居を変わるとかの問題では重要になってくる場合があります。
結果として、始めからコンジャンクションとして観察しているのと同じ事? ではないのです。サインによるクォータイル・アスペクトにはクォータイル・アスペクトとしての影響を持ち、サインによるトライン・アスペクトはトライン・アスペクトのちゃんとした影響が出ます。
惑星の入り込んだサインは、惑星の色を帯びます。しかし場所としての性質を失うわけではありません。Hot & Dry な牡羊のサインに入った惑星と、獅子のサイン、射手のサインは同じ Hot & Dry という性質の場所同士でアスペクトするわけです。最大級の良さを与えてくれると期待できそうです。
この他に、ディグニティーやレセプション、他の惑星の影響を考慮しなければいけないのは占星学上当たり前のことです。アスペクトというラインは引かれたよ、オーブの深さに準じて強さの関係ができ、その内容は、惑星の四つの性質、サインの四つの性質、ディスポジション、ディスポジター、レセプション等を考慮していきます。
2021年6月21日(夏至・月曜日)
● インコンジャクト(in-conjunct)
1世紀のマニリウスが既に書いています。じゃあ、アスペクトなのかですが、英語で書かれている意味をよく見てください。接頭語のinは、否定語です。conjunct(接合)して(in)いない、と、既に書かれているのです。つまり、アスペクトではないことを、インコンジャンクトと言いました。
ネイタル・リーディングの本 | 推薦図書 『星の階梯シリーズ』